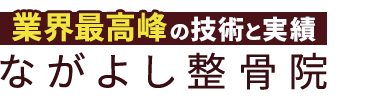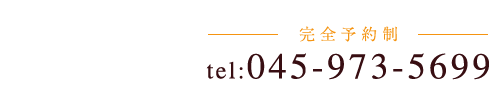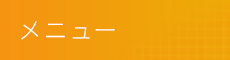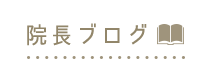1,脊柱の関節機能障害の諸段階
①外傷やストレスにより椎間関節が偏位し、関節の機能が障害される
②求心路を通じて関節の位置に誤った信号が脳に送り続けられる
③非生理的な関節のアライメントによって負荷を受ける関節を代償保護システムとして、関節周囲の筋がスパズムを起こす。
④関節の異常なアライメントを通じて、関節付着部の硬膜が緊張する
⑤異常な関節運動を生じ、可動性減少や代償性の可動性亢進を生じる(joint play)
⑥関節機能障害が靱帯・腱・関節包に不適切な負荷を与える。組織損傷や修復再建を通じて侵害受容器が刺激される。
⑦椎骨が力学的圧力を受けると、うっ血や浮腫が生じ血管や神経の出入り口である椎間孔の内径が狭まり、血管や神経の流れが妨げられる。
2,関節機能障害が神経系に与える影響
①圧迫に対する生理的反応出は、脊髄や脳における神経伝達が活発になる(活動亢進)。
しかし関節機能障害が生じると神経の信号伝達が無制御になる。その結果、脳からの反応として標的間に与える刺激が過剰または過少になる。
②神経が長期に圧迫されると、神経が変性し標的機関への支配が低下する。この結果、筋の変性、身体の自己知覚の異常、腺の機能低下などが生じる。
③神経の変性は、組織の適切な機能を妨げる。すなわち、防御機能の低下や感染症の頻度が高まり、組織が破壊され、機能が制限される。
これらの障害を矯正しなければ、健康状態から病的状態に向かい、最終的に病気を誘発する。
代償期と非代償期
人間は機能障害のある関節の負荷を軽減するために、姿勢の変化を通じて1つの関節の負荷を軽減すると、自動的に他の関節への負荷を生じる。
代償期
異常な負荷に対し自覚がないことが多い。一つの関節に非生理的な負荷が生じ、長期化すると、更に他の関節でも機能障害が生じる(代償性の関節機能障害)。
非代償期
関節機能障害が代償性の機能障害を伴うと、機能障害を起こす関節が増え、期間が長くなる。その結果、ある時点から、もしくはある事象からもはや代償できなくなる。これを非代償期という。患者の身体は組織の損傷を食い止めようとして痛覚が刺激されて痛みとして現れる。
悪化のスパイラル
関節機能障害により損傷された組織は、関節機能障害により組織の血管や神経が傷害されているため、ゆっくりと不十分にしか治癒しない。
また、治癒不良の組織は傷つきやすく、さらなる破壊や再発をもたらすこともある。このようにして悪化のスパイラルに入る。
発生学
人間の身体は外肺葉、中胚葉、内胚葉から発生する。
体節形成
硬節
皮節
筋節
ヘッド帯
内臓知覚性は脊髄神経を通じて伝えられる。
ドギエル細胞は脊髄神経節に存在し、交感神経系(自律神経系)と体性神経系をつなぐ。この伝達は双方に行われる。
脊髄でうっ血が生じると、その刺激はドギエル細胞を通じて患部(髄節)が支配する筋の感覚神経線維に伝わり、この筋で疼痛が生じる。ドギエル細胞を通じた伝達は後根神経節を介してのみ行われる。
これらの疼痛が易刺激性の低い器官から易刺激性の高い器官へ伝達される。ただし、疼痛の伝達は同じ髄節から出る神経の支配をうけるこれらの器官の間でのみ行われる(ヘッドの法則)
脊髄の充血は椎骨骨膜に軽度の充血を生じ、この疼痛はドギエル細胞を通じて皮膚の感覚神経線維に伝えらる。
刺激を処理する脳の中枢は、髄節から伝達された内臓刺激の発生場所を正確に特定できず、内臓の疼痛を刺激を伝えた髄節の神経が支配する皮膚領域や筋肉で発生した疼痛として誤って判断をする。
内臓疾患では過敏になる皮膚領域(痛覚過敏帯)がある(ヘッド帯)
また、髄節の神経が支配する筋肉にも疼痛は伝えられる(マッケンジー帯)
これらは関連痛と呼ばれる。
3,神経解剖学
中枢神経
高等生物の複雑な機能は中枢神経系により可能となっている。
中枢神経は硬膜で覆われている。硬膜内には髄液が存在し、中枢神経への栄養および緩衝作用の役割がある。
末梢神経
脊髄神経は脊髄硬膜を外側へ折り返し、椎間孔を通って外に出る。これにより解剖学的に中枢神経から末梢神経へ移行する。
末梢神経系は体性神経系と自律神経系に分けられる。自律神経系は脳の視床下部で制御され、視床下部は大脳辺縁系により制御されている。
交感神経系
交感神経は脊髄(C1~L1からL3まで)の側角に存在する。攻撃、恐怖、ストレス、不安、重労働などの状況で身体機能を高める(内臓機能は抑制する)。
交感神経は脊髄から出て、脊髄神経の前根を通り、白交通枝を通って交感神経管神経節に達する。神経節に入った後、ニューロンは灰白交通枝を通って再び脊髄神経に入り、脊髄神経に伴行し効果器に達する。
副交感神経系
副交感神経は交感神経と反対の作用を有し、期間の運動および分泌作用を促進する。
副交感神経に由来するニューロンは脳幹および仙髄部に存在する。
頭部
脳幹の神経幹に存する。
Ⅲ:動眼神経
Ⅶ:顔面神経
Ⅸ:舌咽神経
Ⅹ:迷走神経
仙髄部
S2-S4の仙髄
副交感神経核
中間帯の外側部分
後角の腹側部分
4,髄節と脊髄神経
脊髄神経
感覚神経線維(遠心性)は脊髄神経節を経て、後角に入る。
運動神経線維(求心性)は前角から出る。
さらに胸椎および腰椎では側角から自律神経線維も出る。これは遠心性繊維であり、前角を通って脊髄を離れる。
灰白質である後角には情報が集まり、判別されて適切な部位へと転送される。灰白質では介在ニューロン(感覚ニューロンと運動ニューロンの間にあるニューロン)を通じて多シナプス反射が生じる。
脊髄神経は椎間孔を出てすぐに4つの神経枝に分かれる。
①後枝
感覚神経として皮節(デルマトーム)や椎間関節の関節包に伸びる。
側枝を通じて上下椎体にも伸びる。また運動神経として固有背筋を支配する。
②前枝
運動神経として筋節に伸びる。各部位で頚神経叢、腕神経叢、腰神経叢、仙骨神経叢を形成する。
③交通枝
自律神経として内臓節(ヘッド帯)へ伸びる。交感神経幹を通り体内に入る。
④硬膜枝
感覚神経および交感神経の神経枝。脊柱管へ戻り、骨膜、硬膜、硬膜外血管、後縦靭帯、椎間板の繊維輪の最外層へ伸びる。
脊髄神経節
脊髄神経節は脊髄神経の後根に存在し、体性神経系に属する。ニューロンや衛星細胞が皮質ゾーンに集まっている。
脊髄神経には偽単極性ニューロンが存在する。これらは双極性ニューロンから発生する。双極性ユーロんのそれぞれの起点が近づき癒合してひとつの幹となる。これが幹細胞から遠ざかり、末梢性軸索と中枢性軸索ができる。
脊髄神経節にはドギエル細胞も存在する。交感神経からの刺激はドギエル細胞を通過することで修飾され、体性神経へ伝えられる。
脊髄神経細胞の機能的特徴
脊髄神経節細胞では様々な神経ペプチドが検出されている。
P物質
CGRP
アミノ酸(グルタミン酸) など
これらのペプチドは神経細胞体で作られ、軸索輸送され、中枢神経突起に入る。ここからペプチドは放出され、中枢神経に信号を与える。
またペプチドは末梢神経突起にも入り、血管拡張などの重要な生物学的機能を開始させる。
脊髄神経節細胞は、求心性ニューロンであるが、ペプチドを放出するため局所効果器機能を有する。情報を脊髄や脳へ伝達し、存在する各器官で能動的に活動する(ペプチドを放出する)。このため「行動する伝達者」とも呼ばれる。
感覚ニューロン(脊髄神経節細胞)が放出するペプチドは、神経免疫相互作用にも関与している。
(例)
P物質 ⇒ 成熟Tリンパ球および成熟Bリンパ球における免疫グロブリンの合成促進
※胸腺、リンパ節、骨髄、脾臓には感覚神経終末が存在する。
また、一次性求心性ニューロン(脊髄神経節細胞)は炎症にも関与している。炎症を有する組織では、感覚神経線維の側枝が発芽する。
軸索輸送
神経における物質の流れは以下に分類される。
細胞体遠心性
細胞体から突起末端に向かう流れ。ペプチド輸送を行う際の輸送経路。
細胞体求心性
突起末端から細胞体に向かう流れ。細胞体への栄養供給が行われる。また、神経支配をうける組織及び中枢神経から出る成長因子は、ニューロンに影響を与える。
脊髄神経節細胞の末梢神経の突起が損傷すると、節前節後の変性萎縮が生じる。つまり、遠位で末梢神経が切断されて生じる変性(ワーラー変性)だけではなく、脊髄にある中枢神経突起の末端が細胞科学的・機能的に損傷する。この損傷は逆行性の軸索輸送が阻害さることにより、神経成長因子が軸索から細胞体へ届かなくなることで生じる。これらは軸索が再生すれば萎縮は後退し、中枢神経突起の末端の細胞が増殖し再生する。
神経線維の種類
脊髄神経の神経線維には3種類ある。
①運動神経線維:筋を支配する
②感覚神経線維:受容器を通じて得た情報を脳に伝達する
ー機械受容器:圧迫、伸長、振動
ー温度受容器:温度
-化学受容器:科学的刺激
ー侵害受容器:疼痛(炎症や組織の損傷による)
③自律神経線維
脊髄路
求心路
脊髄上行路(求心路)には以下の3つがある
①後索路
身体内部(固有感覚や自己知覚)からのかすかな知覚や細やかな触覚、意識される深部感覚(判別性感覚)を伝える新経路。この新経路は受容器から出て、後角でのニューロンの切り替えを行わず、延髄に直接達する。
②脊髄視床路(前側索系)
大まかな知覚、痛み、圧、温度を伝える神経路。この神経は後角から出て脳の視床に達する。
③脊髄小脳路
後角の細胞から出て小脳に達する。関節、筋、腱の位置情報(固有感覚情報)を伝える。
遠心路
脊髄下行路には以下の2つがある
①錐体路(皮質脊髄路)
大脳皮質の運動野から出て前角(運動神経細胞)に直接入る。
②錐体外路
錐体路以外のすべての遠心路である。錐体外路も前角に入る。
脊髄の反射複合体
髄節は「管理的機能」を有する。
灰白質のある前角は身体からもたらされる「膨大な情報」を処理する脳の負担を軽減するための管理を行う。前角は情報の妥当性により情報を脳に送るべきかを判断する。すべての情報が脳にとって必要ではなく、脳に送るべきものと、髄節だけで対応(反射)しうるものがある。
(例)デルマトームが受傷すると、周囲の筋は緊張し、血管は収縮する。神経支配や血液供給が低下し、この皮膚領域と繋がる内臓(ヘッド帯)は最適に機能できなくなる。
髄節への刺激が長引き、反射反応は持続すると、長期的に髄節へと繋がる内臓で機能障害や疾患が生じることもある。例えば、椎骨の関節機能障害では、椎骨が存する分節の髄節が頻繁に刺激され、反射反応の回数が増える。
内臓反射と内臓ー内臓反射
内臓求心性繊維と内臓遠心性繊維はいわゆる反射弓でつながっている。内臓で生じた興奮は反射弓をを通り、次の器官で反射反応が生じる。
①内臓(内臓反射)
②血管(血管運動反射)
③汗腺(発汗反射)
④立毛筋(立毛筋反射ー鳥肌)
神経への栄養供給は、神経における血管の拡張・収縮により制御されている。不適切な刺激を受けると、神経の生理的作用が変化する。反射弓の外部で生じた非生理的な刺激が神経に作用すると、それが機械的刺激、浮腫などのその他の刺激に関わらず、反射弓の正常な働きが阻害される。反射弓の阻害は求心路から遠心路にも影響を与える。
神経系は自らの栄養供給だけでなく、周囲の組織の栄養供給も制御している。これは血管運動反射を通じて行う。血管運動反射は脊髄の灰白質または延髄のいずれかを期限として発生する。末梢からの刺激が上手く伝わらなくては、延髄も脊髄も正常に機能しない。これらが正常に機能しなければ、血管の収縮および拡張に異常が生じる。
混合性反射
混合性反射には、内臓体性反射と体性内臓反射がある。
内臓ー体性反射
内臓の求心性神経線維を起点として、脊髄の介在ニューロンを経由して運動ニューロンに直接的に反応する。消化器官でみられる、いわゆる筋性防御(デファンス)では、筋肉を支配する神経は、疾患を有する器官と同じ高さの髄節から出ている。
体性ー内臓反射
内臓が皮膚刺激に反応して生じる。秘封の疼痛性刺激は体性内臓反射を生じ、血管収縮神経および汗腺刺激神経(汗腺)に影響を与える。
硬膜枝の機能障害
硬膜の生理学
硬膜枝はごく薄い神経枝である。脊髄神経から出て神経孔をとおり、脊髄に戻る際、椎体のごく近くを走行する。
硬膜枝は脊髄に戻る際に上行枝と下行枝に分かれる。また、硬膜および後縦靭帯で高密度の神経網を形成する。後縦靭帯の硬膜枝は骨膜や椎間円板を支配する。
硬膜枝の運動神経線維は、脊髄の側角で起始し、椎間孔を通り分岐する。分岐した枝は更に進んで再び硬膜の一部として統合され、硬膜孔をとおり、脊柱管の一部として外側へ走行した後、脊髄神経の一部となり脊髄に入る。
このように各髄節では、短い反射弓を通じて、神経の自給(栄養供給)が必要に応じて制御されている。
反射弓を刺激するもの
神経孔を通り椎体に隣接する神経は、機械的に刺激に暴露されている。この機械的刺激は反射弓にとって不適切な刺激となりうる。したがって、椎骨のサブラクセーションは不適切な刺激が生じる原因となりうる。脊柱の静力学的変化でも、椎間孔の内径が変化し、血管や神経に影響を与えることがある。
椎間孔で神経が機械低刺激を受けると、様々な神経線維の反射的活動が持続定期に阻害される。これにより髄節で反射反応や栄養供給が損なわれるだけでなく、髄節の神経が支配する内臓や組織にも影響が及ぶ。
反射弓の刺激による反応
後根にある脊髄神経節の一部は椎間孔に存在する。脊髄神経節は、一次性求心性神経細胞の集まりであり、ドギエル細胞を通じた刺激伝導の中枢である。脊髄神経節が刺激を受けることで一連の反射反応が生じる。
発汗反射の変化
通常では内分泌腺は血中ホルモン濃度が低下すると、ホルモン産生を刺激される。ホルモンの不足は特定の感覚神経終末に検知され、活動電位を通じて伝達され、脊髄の反射弓を通じて運動エネルギーに変換される。
これにより血管運動が変化し、ホルモン産生が低下している内分泌腺に血液供給が増える。さらに、標的の内分泌神経は供給された血液から栄養素を吸収するように促す。血中ホルモン濃度が低下すると、神経終末が刺激されず、神経の活動をさせる反射が生じなくなる。血中ホルモン濃度が正常に戻ると、自動的に内分泌腺の活動が低下する。
内分泌腺の過剰な活動は、反射を引き起こす刺激が強まって生じる。求心性神経線維および後根神経線維は、機械的刺激を受けて興奮する。刺激は、ホルモンの必要性とは無関係にホルモンを分泌し、内分泌障害を生じる(例:バセドウ病)
また、反射弓が抑制されると内分泌は不活動になる、徐々に萎縮する。各器官もこれに応じた活動を行うようになる(不活動の法則)。
血管運動反射の変化
不適切な刺激が神経に与える重大な影響として、刺激を受けた神経の支配領域で重度のうっ血が生じる。このうっ血は、血管運動反射を生じる感覚神経線維が強く刺激されている。
血管運動刺激は、後根の脊髄神経節に存する偽単極神経細胞に伝えられる。偽単極神経細胞の突起が過剰な刺激をドギエル細胞や介在ニューロンに伝えると、交感神経系の反射弓が閉じられる。そこからさらにドギエル細胞は交感神経刺激を一つまたは複数の体性感覚神経線維に伝える。
神経が圧迫されて生じる疼痛は、この神経の髄節が支配する皮膚および筋の感覚神経線維に伝わる。この疼痛は皮膚の疼痛や筋痛として知覚される(ヘッド帯、マッケンジー帯)。
器官の慢性充血により関連痛が生じることもある。器官の慢性充血は椎骨のサブラクセーションにより生じることがある。
充血
硬膜枝は、椎骨のサブラクセーションにより刺激されて広範囲で様々な結果が生じる。
第一に局所性充血が生じる。血管の拡張を通じて骨膜が膨張し椎間孔が狭小化する。これにより更に硬膜枝がさらに強く刺激され、悪循環が生じる。また、硬膜枝は脊髄の血液供給を制御しているため、脊髄でも充血が生じやすくなる。
脊髄の充血は自動的に椎骨骨膜の軽度の充血を生じる。椎骨骨膜に伴う疼痛は、ドギエル細胞を介して椎骨に属売る神経が支配する皮膚の感覚神経線維に伝えられる。
強い刺激を受けて管運動反射が強まると、骨膜や靱帯で重度の充血が生じる。その結果、棘突起骨膜および椎骨周囲の筋が過敏になり、温度が上昇する。この温度上昇はサブラクセーションの位置の特定に役立つ。
関節と筋の悪循環
自由に動く関節では、筋が均衡し関節包が伸び広がり、関節包の受容器が刺激されることもない。しかし、関節機能障害や異常な負荷がかかると、受容器が刺激され、受容器は後角を経由させていた情報を、反射的に前角(運動神経が存在する)に切り替える。同時に、求心性神経を通じて情報を脳幹や脳皮質に送る。
脳は遠心性神経(運動神経線維)を通じて、前角の運動ニューロンに作用する。
(例)錘内筋繊維(筋紡錘にある筋線維)が収縮すると筋紡錘の中央部分が伸長し、筋紡錘の感度が高まる。その結果、安静時でも筋トーヌスが亢進する。
脊髄神経の絞扼による機能障害
脊髄神経が硬膜や椎間孔から出る部位では、脊髄神経が圧迫される危険性が高い。また、これらの部位では動脈や静脈が影響を受ける。特に静脈は5-10mmHgの軽い圧迫でも血液排出は滞る。
血流が止まると、血圧により血液が周囲の組織へ漏れ出る。漏れた血液により浮腫が生じる。この浮腫は更に血管および周囲の組織を圧迫する。また、血液供給が減少すると、組織に十分な栄養が供給されず、老廃物は規則的に処理されない。組織は低酸素状態になり、重度の疼痛が生じる。
圧迫が120mmHgまで強まると、神経組織が破壊され、神経の情報伝達が遮断される。
髄膜と脊髄硬膜
中枢神経を覆う膜は硬い膜(硬膜)と柔かい膜(クモ膜、軟膜)に分けられる。
脊髄硬膜は繊維の多い張りのある結合組織で出来ている。脊髄硬膜のすぐ下にはクモ膜がある。脊柱管内では硬膜は2つの層(骨膜層と髄膜層)に分かれる。これらの間には硬膜外腔があり、脂肪細胞や椎骨静脈叢が存在する。
脊髄硬膜は脊髄の一部であり、ピンと張った状態で脊柱管の中に存在する。脊髄硬膜は脊髄の非生理的な動きに抵抗する。遠位の脊髄神経節では、脊髄硬膜は末梢神経の神経周膜および神経上膜へ移行する。
脊髄硬膜はわずかな骨付着部しか有さない。
大後頭孔の周囲
C2、C3の腹側
S2
付着部間は固定されていない。このため、脊柱は脊髄硬膜との間で緊張を生じることなく動くことが出来る。
脊髄円錐(脊髄の下端)と連続する外終糸(硬膜終糸)は第2尾椎で停止する。ここで終糸は骨に固定され、前仙尾靱帯と連続して繋がる。