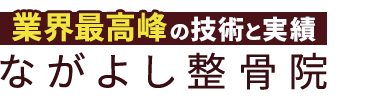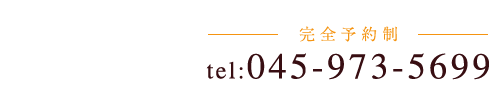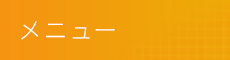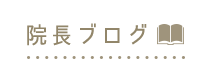記事の筆者:永吉健志郎
「朝起きて一歩目が痛い」「歩くたびに足裏がズキズキする」——そんな足底の痛みに悩んでいませんか? それは、足底筋膜炎の可能性があります。
足底筋膜炎は、単なる足裏の炎症ではなく、足の構造や動き方に深く関連する障害です。 当院では、足底筋膜炎に対するアプローチとして、まず足の機能的な評価を徹底しています。 今回は、実際の臨床で行っている「足底筋膜炎の足の特徴チェック5選」を、最新の医学的根拠とともにご紹介します。
足底筋膜炎とは?
足底筋膜炎は、かかとから足趾の付け根までをつなぐ「足底筋膜」に炎症や微細損傷が生じる状態です。 長時間の立位や歩行、走行などで繰り返し負荷がかかることで、筋膜が引っ張られて炎症を起こしやすくなります。
症状としては、以下のような訴えが多くみられます:
-
朝の一歩目で強く痛む
-
長時間立っているとジンジン痛む
-
かかとの内側に圧痛がある
特に重要なのは、足の機能評価を通じて根本原因を見つけることです。
足の障害は少しのストレスや負担の積み重ねで発症します。そのストレスの原因をみつけて改善す津ことが、足底筋膜炎を根本的に改善するための最短のルートとなります。
足底筋膜炎の足の特徴チェック5選
では、具体的にどのような特徴があるのかをみていきましょう。
① Windlass(ウィンドラス)機構が働いているか?
Windlass機構とは、足趾(とくに母趾)を背屈させると、足底筋膜が巻き上げられ、内側縦アーチが引き上げられる生体力学的反応です。
この機構が正常に働かないと、歩行時に足底筋膜が過剰に引き伸ばされ、痛みの原因になります。
チェック方法:立位または座位で足趾を手で背屈させ、土踏まずが持ち上がるかを観察。
参考:
-
Bolgla et al. 2004『Plantar Fasciitis and the Windlass Mechanism』https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC385265/
-
Shinohara et al. 2025『Dynamic control of medial longitudinal arch』https://www.nature.com/articles/s41598-025-97477-3
② 足趾+足関節の同時背屈(足底筋膜伸長テスト)
足底筋膜は、かかと〜アキレス腱〜足趾まで一連の筋膜ラインを形成しています。 この連動性が失われると、足底に牽引ストレスが集中し、痛みを起こします。
チェック方法:足関節と足趾を同時に背屈し、足底筋膜の伸張痛の有無を確認。
参考:
-
Green et al.『Weight-bearing Dorsiflexion and the Windlass Mechanism』https://www.orthopt.org/uploads/Green.pdf
③ 足関節の背屈可動域(WBLT:Weight-Bearing Lunge Test)
足関節の背屈制限は、歩行時に前方への荷重移動を妨げ、足底への負荷を増大させます。
チェック方法:壁からつま先を10cm離し、膝を壁に近づける。膝がつかない場合は背屈制限あり。
参考:
-
Bennell et al. 1998『Reliability of the weight-bearing lunge test』https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9877344/
-
Dreher et al. 2022『Normative WBLT values in adolescents』https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9517286/
-
PhysioPedia『Knee to Wall Test』https://www.physio-pedia.com/Knee_to_Wall_Test
④ 立位での過回内(オーバープロネーション)
足部の過回内は、内側アーチの低下や偏平足を引き起こし、足底筋膜に持続的なテンションを加えることになります。
チェック方法:立位で踵・アキレス腱の軸が内側に傾いていないか、土踏まずが潰れていないかを確認。
参考:
-
SELF Magazine 2025『Do You Have Plantar Fasciitis?』https://www.self.com/story/plantar-fasciitis-signs-and-treatment
-
Haddad et al. 2023『The Damage and Treatment of Foot Pronation』https://www.researchgate.net/publication/389233751_The_Damage_and_Treatment_of_Foot_Pronation
⑤ タオルギャザーでの足趾の屈曲・内転の協調性
足趾の屈筋(屈筋支帯・母趾外転筋・虫様筋など)の協調性が低下すると、足底筋膜に局所的な負荷が集中しやすくなります。
チェック方法:タオルを足趾で引き寄せる「タオルギャザー」を行い、各指のスムーズな協調性を観察。
参考:
-
Ridge et al. 2017『Reliability of Intrinsic Foot Muscle Strength Tests』https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5723035/
-
Jeong et al. 2024『Toe Flexor Training Improves Foot Arch Stability』https://www.mdpi.com/2076-3417/14/21/9842
まとめ:症状だけでなく「機能」を診る時代へ
足底筋膜炎は、単なる炎症ではなく、「足の機能障害」として捉えるべき疾患です。 今回ご紹介した5つのチェック項目を通じて、足の構造的・動作的な問題点を明確にすることが、根本改善と再発予防につながります。
「湿布や痛み止めだけでは良くならなかった…」 「インソールを使っても再発してしまう…」 そんなお悩みをお持ちの方は、
●足の構造と動作の“本質”を評価・治療する
●根拠に基づいた検査で再発を防ぐ
●全身から診る整骨院の専門的なサポートを受ける
当院では、こうしたアプローチを徹底しています。
📍横浜市青葉区で足底筋膜炎にお悩みなら「ながよし整骨院」へ
完全予約制|専門的なカウンセリング|再発予防までサポート