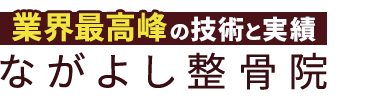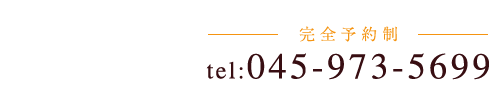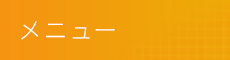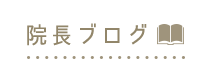この記事の筆者:永吉健志郎
頭痛の本当の原因と生活習慣改善・整体・栄養療法による対策を詳解。緊張型頭痛・片頭痛・群発性頭痛・低血糖・鉄欠乏などすべてまとめた記事です。
はじめに:この記事を読むべき理由
あなたは「頭痛」に長年悩まされ、病院での検査では異常が見つからず、痛み止めでごまかしているだけの生活を送っていませんか?本当の原因にアプローチしない限り、薬で痛みを抑えても再発を繰り返すだけ。
この記事では、
-
頭痛の統計データと傾向
-
3つの主な慢性頭痛タイプの性質と特徴
-
なぜ薬では改善しないのかの理由
-
整体・生活習慣・栄養療法などの有効な対策
-
「機能性低血糖」や「隠れ鉄欠乏」などの体質的要因
について、10,000文字以上の情報量で分かりやすく解説します。
頭痛に悩む人へ──よくある症状と背景
以下のような方に本記事はおすすめです:
-
病院で検査しても「異常なし」と言われたのに頭痛が続く
-
夕方以降や夜間にズキズキと悪化する頭痛
-
数年以上慢性的な痛みが続く
-
首・肩こりと連動する頭が締め付けられるような痛み
-
季節の変わり目や気温差、天候の変化で頭痛が頻発する
これらは慢性頭痛や体質的な傾向と密接に関連している可能性があります。
頭痛の統計データ:年齢・性別・地域の実情
日本における片頭痛の有病率
-
全国調査によると、男性3.6%、女性12.9%、合計8.4%が片頭痛と診断されています。特に30〜40代女性で多発しています 出典 PubMed
-
別のデータ(21,480人対象)では全体3.2%、30〜39歳女性で7.4%、男性1.7%で、女性は男性の約4.4倍でした 出典 Taylor & Francis Online+14Frontiers+14ResearchGate+14
緊張型頭痛(Tension‑Type Headache/TTH)の世界的傾向
-
世界的には、緊張型頭痛は全頭痛の約90%を占め、約19億人に影響するとされています。このうち慢性型は約3% 出典 ウィキペディア+2ウィキペディア+2
-
日本においても、緊張型頭痛は非常に多く報告されており、都市部での長時間デスクワークやストレス文化が背景にあります 出典 ウィキペディア+5Frontiers+5Frontiers+5
頭痛の分類:一次性 vs 二次性
一次性頭痛(慢性頭痛)
-
検査で異常が見つからず、頻繁に起こる頭痛。代表的なものは「緊張型頭痛」「片頭痛」「群発性頭痛」など。
二次性頭痛(危険な兆候を伴う)
-
脳腫瘍、くも膜下出血、髄膜炎、血管障害などの疾患に伴う頭痛。
-
特に「突然の激痛」「意識障害」「麻痺や視覚異常を伴う頭痛」は即受診が必要です。
緊張型頭痛を深掘り:原因・症状・分類・対処法
-
種類
-
稀発性型(~月1回未満)
-
頻発性型(~月15日未満)
-
慢性型(15日以上/月)
-
-
原因と特徴
-
首・肩の筋肉の緊張、長時間の不良姿勢、ストレスや疲労、目の使い過ぎ
-
鈍い圧迫感や締め付け感、後頭部や側頭部に広がる痛み、肩コリと連動、吐き気などの随伴症状は少ない
-
-
改善アプローチ
-
整体やマッサージによる筋肉緩和、姿勢調整、血流改善ストレッチ
-
睡眠の質向上、スマホやPC使用の見直し、運動習慣導入
-
片頭痛を理解する:特徴・随伴症状・改善策
-
特徴
-
随伴症状
-
吐き気、光・音・匂いへの過敏、疲労、倦怠感、閃輝暗点など。
-
-
疫学的傾向
-
日本では年率6.0〜8.9%とされ、多くは30〜40代女性に集中 出典 BioMed Central+1
-
-
改善策
-
マグネシウム、ビタミンB2、ビタミンC、オメガ‑3などの栄養指導
-
引き金となる食品(チーズ、チョコレート、赤ワインなど)回避
-
整体や自律神経の調整による治療
-
群発性頭痛の実態と対策
群発性頭痛は、頭痛の中でも特に稀であり、痛みが非常に激しいことで知られています。1000人中1人程度の頻度で発症し、多くは男性、特に20〜40代に多く見られます。
主な特徴
-
片側の眼の奥に突き刺すような痛み
-
発作は1日に1〜8回ほど、毎日決まった時間帯に発生
-
痛みは15分~3時間続く
-
涙や鼻水、瞼の腫れ、顔の発汗などの自律神経症状を伴う
-
発作中はじっとしていられないほどの痛み
発症要因
現在のところ明確な原因は分かっていませんが、三叉神経と自律神経の異常な連動や、視床下部の異常が関与しているという説が有力です。アルコール、強いにおい、気圧の変化などが誘因となることもあります。
改善と対策
-
酸素吸入療法やトリプタン系薬剤の使用が一般的
-
当院では、首や後頭部の神経・筋肉を緩める施術や、生活リズムの改善、睡眠の質向上も併用します
-
患者様の中には、整体と栄養指導で1年以上再発がない方もいますが、慎重な経過観察が必要です
頭痛の発生メカニズム:何が痛んでいるのか?
頭痛というと「頭そのものが痛い」と感じますが、実際に痛みを感じるのは頭部の筋肉、神経、血管、硬膜など、痛覚を持つ組織です。
外部組織
-
筋肉:前頭筋、側頭筋、後頭下筋群など
-
神経:三叉神経、後頭神経
-
血管:側頭動脈、椎骨動脈など
これらの組織に炎症や緊張が起こると、頭痛が発生します。特に筋肉の過緊張による「筋緊張型頭痛」は整体の対象になります。
内部組織
-
硬膜や脳周囲の動脈・静脈が拡張し、神経を刺激することで拍動性の痛み(片頭痛など)が起こります。
-
三叉神経血管説:三叉神経が刺激されることで神経伝達物質が放出され、血管拡張と炎症を引き起こす
感作(sensitization)
-
末梢感作:神経の過敏化により、些細な刺激で痛みを感じやすくなる状態
-
中枢感作:脳や脊髄が過敏になり、通常は痛くない刺激でも痛みと感じてしまう
これらが慢性頭痛の「治りにくさ」の原因でもあります。
なぜ薬が効かないのか?薬物乱用性頭痛のリスク
多くの方が頭痛時に痛み止めを服用しますが、それが長期間続くと「薬物乱用性頭痛」を引き起こす可能性があります。
薬物乱用性頭痛(Medication Overuse Headache, MOH)
-
市販薬や処方薬(ロキソプロフェン、イブプロフェン、トリプタン系など)の頻回使用によって、痛みに対する感受性が上昇
-
結果的に、頭痛が慢性化・増悪する悪循環に陥る
-
特に1ヶ月に10日以上の使用がリスクとなる 出典
ながよし整骨院での対応
-
薬に頼らず「整体+生活指導+体質改善」で痛みの根源にアプローチ
-
一時的な「症状緩和」ではなく、「再発防止」と「完治」に近づける施術
慢性頭痛と深く関わる2大体質異常
当院に来られる慢性頭痛患者の多くに共通する2つの問題があります。それが機能性低血糖と鉄欠乏です。
機能性低血糖とは?症状と改善策
概要
-
食後の血糖値が急上昇 → インスリン大量分泌 → 急激な低血糖
-
エネルギー不足で神経や脳が正常に働かなくなり、頭痛を引き起こす
主な症状
-
食後の眠気・だるさ
-
夕方以降の強い疲労感・頭痛
-
イライラ・不安感・集中力低下
対策
-
食物繊維を多く含む食品を摂取し、血糖の急上昇を抑える
-
炭水化物や糖質の多い食事を減らし、GI値の低い食品を選ぶ
-
食事間隔を3〜4時間以内にし、空腹を避ける
-
朝食を抜かないことも重要
鉄欠乏(隠れ貧血)の実態と頭痛への影響
鉄不足と頭痛の関係
-
酸素運搬能力が低下し、脳が軽い「酸欠状態」に
-
エネルギー代謝が落ち、自律神経のバランスが崩れやすくなる
特徴的な症状
-
顔色が白い(血色が悪い)
-
爪の変形(スプーン爪)
-
倦怠感・集中力低下・動悸・頭痛
-
月経が重い女性に特に多い
フェリチンを測る重要性
-
ヘモグロビン値が正常でも、**貯蔵鉄(フェリチン)**が極端に低いことがある
-
血液検査ではフェリチン値のチェックを推奨 出典
自分でできる頭痛チェックリスト
慢性的な頭痛に悩む方は、次のようなチェック項目に複数該当する場合、「生活習慣由来の頭痛」である可能性が高いです。
| チェック項目 | 該当する場合の傾向 |
|---|---|
| 朝食を抜くことが多い | 機能性低血糖のリスク |
| 甘いものをよく食べる | 血糖値の乱高下に影響 |
| 顔色が青白いと言われる | 隠れ鉄欠乏の可能性 |
| 夕方になると頭が重い | 血糖や酸素不足由来の頭痛 |
| 市販の痛み止めを週2回以上飲んでいる | 薬物乱用性頭痛の可能性 |
| スマホやPCを1日6時間以上使う | 緊張型頭痛の要因 |
| 月経が重い・量が多い | 鉄分消耗による酸欠性頭痛 |
これらに当てはまる場合は、食事や生活の見直しに加え、整骨院での根本的な調整も有効です。
生活習慣改善の具体策:食事・睡眠・運動
食事面のポイント
-
GI値が低い食品(玄米、オートミール、野菜)を中心にする
-
小麦、乳製品、精製糖を控える(腸内環境改善のため)
-
鉄分を多く含む食品(レバー、赤身肉、ひじき、納豆)を取り入れる
-
よく噛んでゆっくり食べることで血糖値の安定化を図る
睡眠の質向上法
-
寝る前のスマホ・PCを控える(ブルーライトカット)
-
就寝前に白湯やぬるめのお風呂で体を温める
-
寝具を自分の体型に合ったものへ見直す
-
食後2時間以上空けて就寝する
運動・血流改善
-
毎日の軽いウォーキングやストレッチ
-
デスクワーク中は1時間に1回は立ち上がって体を動かす
-
深呼吸や胸郭を開くストレッチで首肩周辺の緊張緩和
よくある質問(FAQ)
Q1:痛み止めをやめたいのですが大丈夫ですか?
A1:自己判断での中止は危険です。まずは整体・栄養・生活習慣の見直しと並行して、医師や専門家と相談しながら段階的に減らすことをおすすめします。
Q2:整体だけで片頭痛は良くなりますか?
A2:片頭痛単独よりも緊張型との「混合型頭痛」の方が多く、整体で効果が出やすいです。ただし、生活習慣の見直しがセットで重要です。
Q3:食生活を改善したらどれくらいで効果が出ますか?
A3:個人差はありますが、2週間〜3ヶ月で頭痛の頻度や強さに変化が現れるケースが多いです。
Q4:鉄のサプリメントを飲めばすぐ良くなりますか?
A4:フェリチン不足を疑う方は、まず腸内環境を整えてからの摂取をおすすめしています。鉄分は消化吸収に負担がかかるため、いきなりの補給は逆効果になることもあります。
Q5:低血糖は病院の血液検査でわかりますか?
A5:通常の血糖値ではわかりにくく、詳細なグルコース曲線や自己観察(日記)から推測することが多いです。
Q6:どのくらい通えば改善しますか?
A6:週1〜2回の通院を2〜3ヶ月続けて頂くと、かなりの症状改善が期待できます。初期は集中して通われる方が効果的です。
まとめ:慢性頭痛に悩んでいるなら、今こそ体質から見直そう
ここまでの要点を振り返ります。
-
慢性頭痛の多くは生活習慣と体質異常に起因
→ 薬だけでは根本解決にならないことが多い -
緊張型・片頭痛・群発性の見極めが重要
→ 混合型の可能性も含めて、症状と生活パターンをチェック -
整体+食事+生活習慣改善が本質的な対策
→ 睡眠、食事、運動、ストレス対策を複合的に
あなたの頭痛も、原因を明確にして、体質から見直せば改善できます。
ご相談は「ながよし整骨院」へ
横浜市青葉区のながよし整骨院では、病院でも改善しなかった慢性的な頭痛や、自律神経の乱れに起因する体調不良の改善に取り組んでいます。
-
丁寧なカウンセリングと姿勢分析
-
個別に合わせた整体と生活指導
-
食事や栄養のアドバイスも提供
詳しくはこちらからお問い合わせください
ご予約・お問合せ